ベンチャー・リンク創業者から「企業家輩出機関」を継承する
1990年代後半から2000年代後半にかけて、東証一部(当時)の経営コンサルティング会社、ベンチャー・リンクで昇竜の勢いで実績を上げつづけていた一騎当千の人物がいた。経営指導を担うSV本部幹部だった大塚誠氏である。大塚氏はベンチャー・リンクに12年在籍して飲食店など約1000店舗の経営改善に従事し、強力無比な使命感と卓越したリーダーシップを発揮していた。その実績をもって、社内ベンチャーで外食事業会社を立ち上げて社長も務めた。
08年、ベンチャー・リンクの倒産危機にともない退職した大塚氏は、IT企業への転職を考えていた。だが、部下たちが大塚氏に起業を要請し、思いを受け入れて4人の部下とともに独立し、もつ鍋店「せかいち」を高田馬場駅前の栄通りに開店する。独立資金は大塚氏に加え4人の部下、さらにベンチャー・リンク時代の同僚、大塚氏の知人など計10人超で拠出し合って賄った。
一見すると必ずしも珍しいケースではないが、この独立は、大塚氏にとって特別な意味をもっていた。ベンチャー・リンクが理念に掲げていた「企業家輩出機関」の継承である。大塚氏は創業者の小林忠嗣氏が居を構える京都市を訪ね、企業家輩出機関を名乗るための承諾を求めた。小林氏は快諾した。大塚氏の手腕への期待だけでなく、おそらく信義を重んずる行為に感服したのではないか。
企業家輩出機関の真意は、単に社員を次々に独立に導くことではない。独立の有無にかかわらず、業を企てられる自立した人材を育成することにある。大塚氏は、自らロールモデルとして実践してきた理念の継承・発展を意図したのでる。

差別化の追求は個客を逃す“NOの排除”で、5年で85店
オープン当初の「せかいち」は相応の収益を出していたが、大塚氏の基準では「普通の水準」だった。フランチャイズ(FC)展開で一気に多店舗化する方針だったが、「圧倒的に勝っていない店をFC展開しても、普通のFCにしかならない」と判断して、大塚氏は自ら路上キャッチをはじめる。空中店舗という不利な立地をカバーする目的もあったが、さらに顧客が店を選ぶ動機をヒヤリングしたのだ。
どの店に入る顧客にも次々に声をかけて「どうして、この店を選んだのですか?」と尋ねて、入店動機を把握していった。この取り組みを5カ月間つづけたこところ、明らかになったことが2つあった。
ひとつは、顧客は入店した時点で店選びが終わっているので、店内でアンケートを取っても意味がなく、店選びの意思決定時にアプローチをしないと集客につながらないこと。大塚氏は「お客さんの行動を見ていると、うちの店が選ばれた理由も外された理由も、ほかの店が選ばれた理由も外された理由も、よく分かってきました」と振り返る。
もうひとつは「NOの排除」である。「せかいち」は尖ったもつ鍋を差別化要素にしていたが、意に反して、これが外される理由になっていた。夜の飲食街を歩く客はグループ客が多く、歩きながら店を選ぶ時に優先されるのは、特定の料理よりも、むしろ皆で楽しく過ごせる場所かどうか。もつの美味しさを訴求すれば「もつは苦手」というメンバーが出てきて外されるなど、差別化によるYESの追求はNOに転換し、街をさまようグループ客への訴求にはならなかった。

「誰かが『この店じゃないと嫌だ』と主張するのではなく、『この店でいいんじゃない』という判断で、皆にとって嫌でない店が選ばれていたのです。集客力を強化するポイントは、YSEの追求ではなくNOの排除であると気づきました」(大塚氏)
NOの排除をどのように実践したのか。キャッチでは自店をアピールせずに顧客の要望を聞き出した。例えば「ピザを食べたい」「寿司を食べたい」「個室で飲みたい」「一人2000円以内で飲みたい」「朝まで呑みたい」などといわれても、すべて実現させた。近隣からピザや寿司を買ってきて用意し、あるいは個室を設営してNOを排除し続けたのである。
声をかけた相手はほぼ100%が来店し、「せかいち」は1日4回転で営業利益率は40%という高収益店に大化けした。その後は「ぶん回すようにして」(大塚氏)多店舗化を進めて、5年間に直営で85店まで出店する。すべて初期投資の低い空中店舗だったが、キャッチによるNOの排除によって、全店とも毎月200万円前後の営業利益を計上しつづけた。
ところが、風向きが一変する。折から悪質なキャッチがのさばりはじめたのを機に、警察が検挙に着手するなど、キャッチが社会問題としてクローズアップされるようになった。大塚氏は全店でキャッチを止め、インターネット集客に切り替えていく。
同時に業態の転換も進めた。ネット上の動線を解析し、店舗ごとにニーズが見込まれる業態を抽出して、店舗のモデルチェンジを図った結果、業態がどんどん増えて、現在は65業態70店舗。これだけの店舗に対して、Globridge(グロブリッジ)は「SCM」(ストア・チェンジ・マネジメント)という概念を創出し、各店舗が商圏特性を踏まえて独自に戦略を立案・実践する運営方法を整備した。
大塚氏は「現場の社員には自分たちで開発した業態なので張り合いがありますが、会社にとっては効率性が課題です」と打ち明ける。

社員に求める高い目標設定達成の有無よりも経験値を重視
Globridge(グロブリッジ)が目指すゴールは「世界一」である。経営理念にも明文化されているが、大塚氏は「本当に世界一になれるかどうかには興味がありません」。真意は何だろうか。
「どのステージをめざすかによって戦略やスピード感が変わってきます。私は外食業界のトップ企業と言うよりも、世界的なアップル、マイクロソフト、セールスフォース・ドットコムなどをベンチマークして、こうした企業のステージまで行って世界一の企業になろうと思っています」
このゴールに向かう事業目的に掲げたのが「食業維新」である。食材の品質向上や伝統的な和食の継承など食産業の課題解決に向けて「本物追求」「現場に頭脳を」「真の食インフラを作る」という「維新三策」に取り組んでいる。
社員数は約200人。企業家になることを求めているが、「企業家輩出機関」を継承した大塚氏が定義する企業家は「自分の責任と自分の決断で自分の未来をつくる人」。この定義をSCMで実践させ、さらに隔週2時間を費やす全社会議で、大塚氏がさまざまな講義を行なっている。育成のポイントは高い目標設定を習慣づけさせること。目標の高低で経験値が大きく異なってくるからで、目標達成の有無よりも経験値の蓄積を重視している。
グロブリッジの2017年8月期業績は売上高44億円。3年後に株式上場を果たすスケジュールを立てて、準備に入っている。

飲食店経営の成功原理が分かるにはよほどの経験値とセンスが必要
豊富な経営指導経験と経営の実践で培った大塚氏の飲食ビジネス論は、原理原則を突いている。
「飲食店家経営は足し算のビジネスです。1店舗の売り上げと利益の足し算であって、多店舗化したところで、それだけで効率化できるビジネスではありません。人が関わるビジネスなので、多店舗化するとQSC(品質・サービス・清潔)が安定せずに躓いてしまいがちです。多店舗化すれば人件費をコントロールするために、パートタイマーを起用せざるをなくなりますが、社員でカバーできる範囲を超えるとサービスに支障が出てしまうのです」
足し算には積み重ね以外の算段しかないが、この原理は、いまの外食市場でどこまで有効なのか。
「たとえば初期投資3000万円をかけて出店して3~4年で回収する計画を立てた場合、3000万円を利益のなかから費用を賄うか、それとも利益を実績に借り入れるのが通例ですが、要するに飛び道具がありません」
だが、こうした現実を把握せずに、飲食店経営は素人でも創業しやすいと曲解されていることは否めない。大塚氏は次のように指摘する。
「日本は世界でも起業しやすい国の1つですが、素人プランにも創業融資が出やすくて、ビジネスの素人が最初にイメージしやすいのが飲食なのです。飲食なら商品を自分で作れて、売り上げがゼロになることも考えにくいじゃないですか。しかもライセンス制がないので、誰でも参入できてオーバーストア状態になっていて、需給バランスが崩れています。
飲食店経営の成功は業態と立地のマッチングで決まりますが、この原理が分かるようになるには、よほどの経験値とセンスが必要です。自分がつくった業態を単純に増やす経営は負けの方程式に入ってしまうと言う事実を理解した方がベターだと思います」
創業期の飲食店経営者にとって、多店舗化の有効な手段は必然的にFC加盟になるという。
「勝つ確率が高いのはFCパッケージです。運営が標準化されているので品質が安定するうえに、自分の能力不足を本部が担保してくれます。開業希望者の大半が失敗する物件調査も、本部がカバーしてくれます。同じ投資をするのなら、自分の業態を多店舗化するよりも、いったんFCに加盟して3~4店を展開したほうが、利益率は下がっても成功できる確率は高いのです。3~4店から次のステージに進めるかどうかが飲食店経営の生命線ですが、そのためにはオーナーが出店を直接手がける必要があり、オーナーの給料の原資と既存店を任せられる体制を固めておかなければなりません。その意味で、成長のステップとしてFC加盟が現実的といえるのです」
飲食店経営に知悉していた自分でも、かりに営業利益率15~20%で多店舗化に入っていたら、いまのグロブリッジは存在しなかった。“普通の経営”とは異なる路線を敷いたからこそ、今日がある。大塚氏はそう思っている。


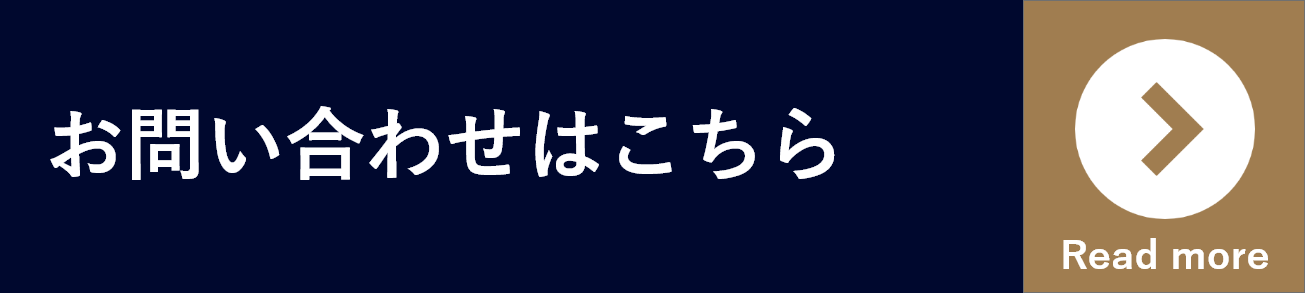
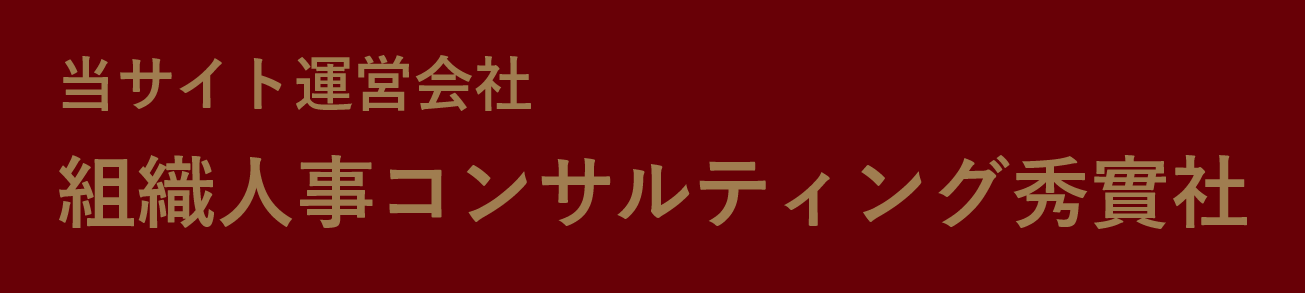
コメント